-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
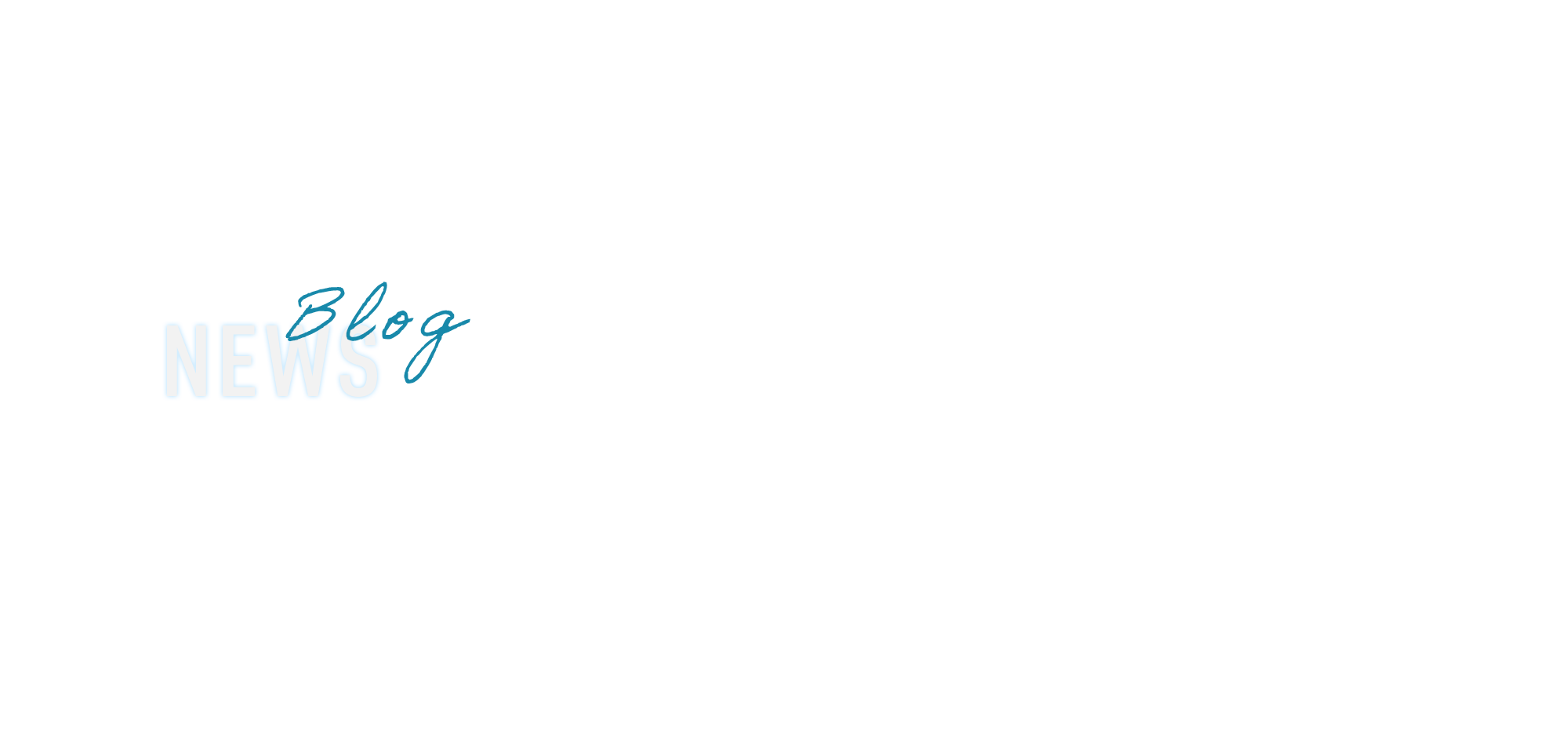
皆さんこんにちは!
長野県松本市を拠点に解体工事など総合建設工事を行っている
安栄株式会社、更新担当の富山です。
目次
~エコ解体が選ばれる時代へ~
近年、解体工事の世界でも
**「環境への配慮」**が強く求められるようになってきました。
その中で注目されているのが、
**環境配慮型解体工事(エコ解体)**です🌍
ただ壊すだけではなく、
環境負荷を抑えながら行う解体工事が広がっています。
エコ解体とは、
環境への影響をできる限り抑えることを目的とした解体工事です。
具体的には👇
低騒音・低振動の施工
廃材の分別・再資源化
CO₂排出量の削減
周辺環境への配慮
などが含まれます。
解体工事で問題になりやすいのが、
騒音や振動です。
エコ解体では、
低騒音型重機の使用
作業方法の工夫
工程管理による音の分散
などにより、
周辺への負担を最小限に抑える工夫が行われています。
環境配慮型解体工事では、
分別解体とリサイクルの徹底が欠かせません。
コンクリート → 再生砕石
鉄 → 鉄鋼原料
木材 → チップ・燃料
といった形で、
廃材は「ゴミ」ではなく資源として扱われます♻️
再資源化率を高めることで、
最終処分場への負担を減らすことができます。
重機の稼働や廃材処理には、
どうしてもエネルギーが必要です。
エコ解体では、
作業効率の向上
重機の稼働時間削減
適切な運搬計画
などを通じて、
CO₂排出量の削減にも取り組んでいます。
環境配慮型解体工事は、
設備だけでなく、人の意識も重要です。
環境を意識した施工
法令順守
地域への配慮
これらを徹底することで、
解体工事は社会に貢献する仕事になります。
環境配慮型の解体工事は、
これからの時代に欠かせない考え方です。
✅ 低騒音・低振動で近隣に配慮
✅ 再資源化率を高め、廃棄物を減らす
✅ CO₂削減で環境負荷を軽減
解体工事は、
未来の街づくりにつながる仕事でもあります🌱
次回もお楽しみに!
安栄株式会社は長野県松本市を拠点に解体工事など総合建設工事を行っております。
お気軽にお問い合わせください。
![]()
皆さんこんにちは!
長野県松本市を拠点に解体工事など総合建設工事を行っている
安栄株式会社、更新担当の富山です。
~解体後に見えないリスクと、次の工事につなげる重要工程~
解体工事が終わり、建物がなくなると
「これで工事は完了」と思われがちですが、
実は**本当に重要なのは“その下”**にあります。
解体後の整地作業中に、
地中埋設物と呼ばれる想定外のものが見つかるケースは、決して珍しくありません🧱
これらは、その後の建築工事や土地活用に大きな影響を与える要素です。
地中埋設物とは、解体後に地面の下から出てくる人工物のことを指します。
代表的なものには👇
古い基礎コンクリート
地中梁・杭
井戸や浄化槽
廃材・ガラ・瓦礫
過去の建物の残骸
などがあります。
これらは、図面が残っていなかったり、
昔の工事が大まかだった場合に、そのまま埋められていることが多いのが実情です。
地中埋設物が残ったままだと、
次のようなトラブルにつながる可能性があります。
新築工事の基礎が施工できない
地盤改良工事がやり直しになる
工期の遅延
追加費用の発生
特に、建築工事が始まってから発覚すると影響が大きいため、
解体工事の段階でしっかり確認しておくことが重要です。
地中埋設物は、
事前の現地調査や、解体後の整地作業中に確認されます。
建物配置の確認
既存資料や聞き取り調査
整地時の掘削確認
これらを丁寧に行うことで、
リスクを早期に把握することができます。
完全に防ぐことは難しいですが、
「想定しておく」ことがトラブル回避につながります。
解体後の土地では、
次の建築に向けて地盤調査が行われることが一般的です。
このとき、
地中埋設物が残っていないか
地盤の状態に影響が出ていないか
が重要なチェックポイントになります。
地中埋設物を適切に撤去し、
きれいな状態で地盤調査を行うことで、
正確な調査結果が得られ、安心して次の工事へ進めます。
地中埋設物と地盤調査は、
解体工事の「見えないけれど非常に重要な部分」です。
✅ 解体後に想定外の埋設物が出ることがある
✅ 事前調査と整地時の確認が重要
✅ 次の建築工事に直結する工程
解体工事は、
次の建物を安全に建てるための準備でもあります🏗️
次回もお楽しみに!
安栄株式会社は長野県松本市を拠点に解体工事など総合建設工事を行っております。
お気軽にお問い合わせください。
![]()
皆さんこんにちは!
長野県松本市を拠点に解体工事など総合建設工事を行っている
安栄株式会社、更新担当の富山です。
目次
~地域特性に合わせた施工計画の重要性~
解体工事は、どこでも同じ方法で行われるわけではありません。
実は、都市部と地方では、解体工事の考え方や施工方法が大きく異なります。
建物の立地や周辺環境に応じた計画を立てることが、
安全でスムーズな解体工事につながります🏗️
都市部では、以下のような条件が重なります。
敷地が狭い
建物が密集している
高層建物が多い
人通りや交通量が多い
このため、解体工事には高度な計画性と技術が求められます。
都市部の解体工事では、
手壊し解体
小型重機の使用
防音・防塵シートの徹底
作業時間の厳守
など、周辺環境への配慮が最優先となります。
特に、騒音・振動・粉じん対策は、
近隣トラブル防止のためにも欠かせません。
一方、地方では、
敷地に余裕がある
周囲に建物が少ない
重機が使いやすい
といった環境が整っていることが多く、
大規模な重機解体が可能です。
その分、工期を短縮しやすく、
効率的な作業が行えるケースも多くなります。
地方では、
大型重機の導入
廃材の仮置きスペース確保
作業動線の確保
がしやすい反面、
敷地が広いことで管理が行き届きにくいという側面もあります。
安全管理や分別管理を徹底することが重要です。
都市部・地方のどちらにおいても大切なのは、
地域特性を理解した施工計画です。
周辺環境
交通状況
敷地条件
建物構造
これらを総合的に判断し、
最適な工法を選択することが、
安全で円滑な解体工事につながります。
都市部と地方では、
解体工事の進め方は大きく異なります。
✅ 都市部:配慮と技術が重要
✅ 地方:効率と管理が重要
✅ 共通:事前計画と安全対策が不可欠
地域ごとの特性を理解し、
最適な解体工事を行うことが成功の鍵です🏗️
次回もお楽しみに!
安栄株式会社は長野県松本市を拠点に解体工事など総合建設工事を行っております。
お気軽にお問い合わせください。
![]()
皆さんこんにちは!
長野県松本市を拠点に解体工事など総合建設工事を行っている
安栄株式会社、更新担当の富山です。
目次
~解体工事が環境に果たす大切な役割~
解体工事というと、「建物を壊す仕事」というイメージが先行しがちですが、
実はその後に続く産業廃棄物の分別とリサイクルこそが、非常に重要な工程です️
解体工事では、建物1棟を壊すだけで、
コンクリート・鉄・木材・プラスチック・ガラスなど、
膨大な量の廃材が発生します。
これらを適切に分別し、再資源化することが、現代の解体工事には強く求められています。
解体現場では、以下のような産業廃棄物が発生します。
コンクリートがら
鉄くず・金属類
木材(柱・床・内装材など)
プラスチック類
ガラス・石膏ボード
これらを一括で処分するのではなく、種類ごとに分別することが、リサイクルの第一歩です。
分別解体が重要とされる理由は、大きく3つあります。
廃材を適切に分別することで、
再利用・再資源化が可能になり、
最終処分場に送られる量を大幅に減らすことができます。
建設リサイクル法により、一定規模以上の解体工事では
分別解体と再資源化が義務化されています。
廃材を分別することで、
リサイクル可能なものは資源として扱え、
処分コストの削減につながるケースもあります。
分別された廃材は、以下のように再利用されます。
コンクリート → 再生砕石として道路工事へ
鉄 → 製鉄原料として再利用
木材 → チップ化して燃料・建材へ
プラスチック → 原料として再加工
解体工事は「壊して終わり」ではなく、
次の資源へとつなげる仕事でもあるのです♻️
産業廃棄物の分別・処理は、
解体業者の意識と管理体制によって大きく差が出ます。
分別ルールの徹底
マニフェスト管理
適正処理業者との連携
これらを確実に行うことが、
信頼される解体工事につながります。
産業廃棄物の分別とリサイクルは、
解体工事における重要な責務です。
✅ 廃材を正しく分別する
✅ リサイクル率を高める
✅ 環境負荷を減らす
解体工事は、
未来の環境を守る仕事でもあることを忘れてはいけません
次回もお楽しみに!
安栄株式会社は長野県松本市を拠点に解体工事など総合建設工事を行っております。
お気軽にお問い合わせください。
![]()
皆さんこんにちは!
長野県松本市を拠点に解体工事など総合建設工事を行っている
安栄株式会社、更新担当の富山です。
目次
解体工事は、
「壊すこと」よりも
**「壊す前の準備」**が重要です。
その中心となるのが、
👉 仮設工事と養生
ここを疎かにすると、
どれだけ解体作業が丁寧でも、
現場全体の評価は大きく下がります。
仮設工事とは、
解体工事を安全に進めるための準備工事です。
主な内容は、
足場の設置
仮囲いの設置
養生シートの取り付け
仮設通路・出入口の確保
これらはすべて、
解体作業そのものを支える土台となります。
足場は、
作業員の安全確保
高所作業の安定
作業効率の向上
だけでなく、
👉 落下物の防止
👉 周囲への被害防止
という重要な役割を担っています。
足場が不十分な現場ほど、
工事が遅れる
事故リスクが高まる
近隣トラブルが起きやすい
という傾向があります。
養生シートは、
単なる「目隠し」ではありません。
粉塵の飛散防止
破片の飛散防止
騒音の軽減
周囲からの視線遮断
特に住宅密集地では、
養生の良し悪しが
👉 近隣の印象を大きく左右します。
養生が不十分な現場では、
洗濯物への粉塵付着
車両や建物の汚損
苦情・工事停止リスク
といったトラブルが発生しやすくなります。
解体工事で最も避けたいのが、
👉 近隣トラブル
だからこそ、
「壊す前の配慮」が何より重要なのです。
仮設工事や養生は、
完成後に残らない
写真に映りにくい
評価されにくい
しかし、
👉 現場を見れば一発で分かる部分
シートの張り方
隙間の処理
足場の整然さ
ここに、その現場の
管理レベル・意識の高さが表れます。
仮設工事と養生は、
解体工事のスタート地点
安全の要
周辺環境への配慮の象徴
解体工事の品質は、
👉 壊す前にほぼ決まっている
と言っても過言ではありません。
見えない準備にこそ、
本当のプロの仕事があります。
次回もお楽しみに!
安栄株式会社は長野県松本市を拠点に解体工事など総合建設工事を行っております。
お気軽にお問い合わせください。
![]()
皆さんこんにちは!
長野県松本市を拠点に解体工事など総合建設工事を行っている
安栄株式会社、更新担当の富山です。
目次
解体工事と聞くと、多くの人が
「大きな重機で一気に壊す」
そんなイメージを持つかもしれません。
しかし実際の解体現場では、
重機が使えない、使ってはいけないケースが数多く存在します。
そこで必要になるのが、
👉 手作業による解体
現代の解体工事においても、決して欠かせない工法です。
手作業解体が必要になる代表的なケースは以下の通りです。
建物同士の距離が極端に近い
隣家が現役で居住中
道路幅が狭く、重機が進入できない
建物の一部だけを解体する必要がある
振動・騒音を最小限に抑える必要がある
特に都市部や古い住宅街では、
「重機が入らない前提」で工事計画を立てることも珍しくありません。
手作業解体は、文字通り
人の手と工具で建物を解体していく工法です。
使用される主な道具は、
バール
ハンマー
電動工具(インパクト・カッターなど)
小型の解体用工具
これらを使い、
天井 → 壁 → 床
内部 → 外部
上から下へ
という順序を厳密に守りながら、
一つひとつ解体していきます。
手作業解体で最も大切なのは、
👉 「壊してはいけないものを壊さない」こと
隣家の外壁
共有している境界部分
地中の配管・配線
周囲の塀や構造物
重機解体と違い、
ミスが即トラブルに直結します。
だからこそ、
建物構造の理解
力のかけ方
崩れる方向の予測
といった、職人の経験値がそのまま安全性につながります。
手作業解体では、
図面だけでは分からない状況が頻発します。
思った以上に梁が太い
壁の中に補強材が入っている
老朽化で想定外の崩れ方をする
こうした場面で重要なのが、
👉 「止まる判断」
👉 「手順を変える判断」
無理に進めるのではなく、
一度状況を整理し、安全な解体方法を選び直す。
これができるかどうかで、現場の安全度は大きく変わります。
技術が進歩し、重機が高性能になっても、
手作業解体がなくならない理由は明確です。
繊細な作業が必要
周辺環境への配慮が必要
部分解体・改修工事が増えている
つまり手作業解体は、
👉 解体工事の“最後の砦”
とも言える存在なのです。
手作業による解体は、
時間がかかる
体力を使う
神経を使う
しかしその分、
精度が高い
周囲に優しい
トラブルが少ない
重機では代替できない価値があります。
解体工事の現場は、
最後はやはり
👉 人の技術と判断力
で成り立っています。
次回もお楽しみに!
安栄株式会社は長野県松本市を拠点に解体工事など総合建設工事を行っております。
お気軽にお問い合わせください。
![]()
皆さんこんにちは!
長野県松本市を拠点に解体工事など総合建設工事を行っている
安栄株式会社、更新担当の富山です。
目次
解体工事の現場で、
ひときわ存在感を放つのが重機です。
しかし、重要なのは
👉 重機そのものではなく、操作する人間
重機オペレーターは、
解体工事の安全性・スピード・精度を左右する
現場の要です。
重機オペレーターの仕事は、
単に建物を壊すことではありません。
崩す順序を考える
荷重のかかり方を読む
周囲への影響を想定する
常に
👉 「どう壊せば安全か」
を考えながら操作しています🧠
現場では、用途に応じて重機を使い分けます。
油圧ショベル
大割機
小割機
フォーク・つかみ機
建物の構造や高さ、周辺環境により、
最適なアタッチメントを選択します。
解体工事では、
数センチ単位の操作
ゆっくりとした力加減
瞬時の判断
が求められます。
特に、
隣接建物が近い
電線がある
地下構造物がある
現場では、
荒い操作は即事故につながります⚠️
優れた重機オペレーターは、
作業員の位置
合図・無線の内容
現場全体の流れ
を常に把握しています。
視界に入らない部分まで想像する力が、
安全を支えています👀
重機オペレーターの熟練度は、
解体スピード
分別精度
工期短縮
に直結します。
無駄な動きが少なく、
一手先を読んだ操作ができるほど、
現場全体がスムーズに回ります。
解体工事では、
転倒
崩落
飛散
といったリスクが常に存在します。
重機オペレーターは、
そのすべてをコントロールする立場。
👉 現場の安全は、オペレーターの判断にかかっている
と言っても過言ではありません。
重機オペレーターは、
力仕事の象徴
花形作業
と思われがちですが、実際は
判断力
集中力
責任感
が極めて高く求められる仕事です。
解体工事の品質と安全は、
👉 重機オペレーターの腕で決まる
それほど重要な存在なのです🚜✨
次回もお楽しみに!
安栄株式会社は長野県松本市を拠点に解体工事など総合建設工事を行っております。
お気軽にお問い合わせください。
![]()
皆さんこんにちは!
長野県松本市を拠点に解体工事など総合建設工事を行っている
安栄株式会社、更新担当の富山です。
目次
解体工事と聞いて、多くの人が思い浮かべるのは
「大きな音」「重機」「建物が崩れる迫力」かもしれません。
しかし、現場で本当に注意しなければならないのは、目に見えない危険です。
その代表が
👉 粉塵(ふんじん)
👉 アスベスト(石綿)
これらへの対策は、解体工事における最重要管理項目のひとつです。
解体工事では、
コンクリートの破砕
内装材の撤去
外壁・屋根材の解体
といった工程で、大量の粉塵が発生します。
この粉塵には、
コンクリートの微粒子
モルタル粉
木材・石膏ボードの破片
などが含まれ、
吸い込むことで健康被害や近隣トラブルにつながる恐れがあります⚠️
解体現場で行われる粉塵対策は、複数を組み合わせます。
最も基本的な対策が散水です。
解体箇所に直接水をかける
粉塵が舞い上がる前に湿らせる
これだけでも、粉塵の飛散量は大きく減少します💧
現場周囲を囲う防音シートは、
騒音対策
粉塵の拡散防止
という二つの役割を果たします。
屋内解体や精密解体では、
集塵機を使用して粉塵を直接吸引します🌀
アスベスト(石綿)は、
かつて「夢の建材」と呼ばれた素材です。
耐火性
断熱性
防音性
に優れ、多くの建物で使用されてきました。
しかし後に、
重篤な健康被害を引き起こすことが判明しました。
アスベストの最大の危険は、
👉 空気中に飛散し、吸い込んでしまうこと
吸入すると、
中皮腫
肺がん
石綿肺
など、数十年後に健康被害が現れるケースもあります。
だからこそ、
現在は法律で厳しく管理されています📜
解体工事では、着工前に必ず
建築年代の確認
建材の事前調査
必要に応じた分析調査
を行います。
アスベストが確認された場合、
行政への届出
作業計画の提出
専門資格者による施工
が義務となります。
アスベスト処理は、通常の解体とは別工程です。
1️⃣ 作業区画の完全隔離
2️⃣ 負圧集塵機の設置
3️⃣ 湿潤化しながら慎重に除去
4️⃣ 専用袋で密閉・搬出
5️⃣ 管理型処分場での処分
「知らなかった」「少量だから」は通用しません。
粉塵・アスベスト対策は、
現場作業員の健康
近隣住民の安心
法令遵守
すべてを守るための解体工事の根幹です。
見えないからこそ、
👉 最も手を抜いてはいけない工程
それが粉塵対策とアスベスト処理です。
次回もお楽しみに!
安栄株式会社は長野県松本市を拠点に解体工事など総合建設工事を行っております。
お気軽にお問い合わせください。
![]()
皆さんこんにちは!
長野県松本市を拠点に解体工事など総合建設工事を行っている
安栄株式会社、更新担当の富山です。
~都市環境と共存する“静かな現場づくり”~
解体工事は、重機を使う大規模作業が多く、どうしても騒音や振動、粉じんが発生します。
特に都市部や住宅密集地では、近隣住民からの苦情やトラブルを防ぐために、
徹底した環境対策とコミュニケーションが欠かせません。
防音パネル・仮囲いの設置
工事現場を防音パネルで囲い、作業音の外部拡散を防止します。
最近では、吸音性の高い軽量パネルも増え、組立て効率と防音性能を両立しています。
低騒音型重機の導入
従来の油圧ショベルやブレーカーに代わり、静音設計の新型重機が普及しています。
機械メーカーも環境基準に合わせたモデル開発を進めており、現場全体での騒音抑制に貢献。
作業時間の制限
早朝や夜間の作業は原則禁止。
地域の条例に基づき、日中時間帯での作業に限定して実施します。
防振マット・防振機械の使用
振動が地盤や隣接建物に伝わらないよう、機械の下に防振材を設置します。
散水・ミスト噴射による粉じん抑制
解体作業中に舞い上がるホコリを防ぐため、
散水やミスト機を活用し、常に湿潤状態を維持します。
近年では自動噴霧システムの導入も進み、作業効率と環境保全の両立が可能になっています。
工事前には、近隣説明会や戸別訪問による事前周知を行います。
工事期間・作業時間・使用機械・安全対策などを丁寧に説明し、理解と協力を得ることが大切です。
また、現場付近には「工事のお知らせ看板」や「連絡先掲示板」を設置し、
何かトラブルが発生した際にもすぐに対応できる体制を整えます。
📣「静かな工事」「誠実な対応」が、信頼される現場の条件。
技術と配慮の両立が、地域と共存する鍵になります。
近年では、騒音・振動のリアルタイムモニタリングを導入する現場も増えています。
センサーを使い、作業状況をデジタル管理することで、
一定基準を超える騒音・振動を自動で警告・記録できるようになっています。
これにより、住民への影響を数値で把握でき、
「どの作業でどれくらいの音が出るか」を科学的に検証・改善することが可能となりました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 騒音対策 | 防音パネル・低騒音重機・作業時間管理 |
| 振動対策 | 防振マット・機械改良・リアルタイム測定 |
| 粉じん対策 | 散水・ミスト噴射・湿潤管理 |
| 近隣対応 | 事前説明・掲示・迅速な対応 |
| 意義 | “安心・信頼される工事”の実現 |
🌿 解体工事は、ただ壊すのではなく「地域の環境と共に進める」仕事。
技術と誠意の積み重ねが、街の信頼を築き上げていきます。
次回もお楽しみに!
安栄株式会社は長野県松本市を拠点に解体工事など総合建設工事を行っております。
お気軽にお問い合わせください。
![]()
皆さんこんにちは!
長野県松本市を拠点に解体工事など総合建設工事を行っている
安栄株式会社、更新担当の富山です。
~“壊す”から“資源を再生する”へ、持続可能な工事のカタチ~
建物の解体は、単なる撤去作業ではありません。
現代の解体工事は、**資源を循環させ、環境負荷を最小限に抑える「再生型工事」**へと進化しています。
その背景にあるのが、2002年に施行された「建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)」です。
この法律により、一定規模以上の建物を解体する際には、
「事前届出」や「分別解体」の義務が課せられ、解体現場にも法的な管理体制と責任が求められるようになりました。
「建設リサイクル法」は、建設工事に伴って発生する大量の廃材を再利用・再資源化することを目的とした法律です。
建設業界では年間で数千万トンもの廃棄物が発生しており、その多くはコンクリートや木材、アスファルトなどの再生可能な資材です。
この法律では、次のような工事を対象としています。
延べ床面積が80㎡以上の建築物の解体
新築・改築で床面積500㎡以上の工事
アスファルト・コンクリート舗装で1,000㎡以上の改修工事
対象工事に該当する場合は、工事着手の7日前までに自治体へ届出を提出しなければなりません。
従来は、建物を一気に壊して“混合廃棄物”として処理することが多く、
大量の廃棄が発生していました。
しかし現在では、資材ごとに丁寧に分けて処理する分別解体が義務化されています。
主な分別対象は以下の通りです。
| 資材の種類 | 再利用・再資源化の方法 |
|---|---|
| コンクリート | 破砕して再生砕石として再利用 |
| 木材 | チップ化して燃料やボード材へ再利用 |
| アスファルト | 再生舗装材としてリサイクル |
| 鉄・銅など金属 | 溶融・再加工して再資源化 |
これらの資源を適切に仕分けることで、
最終的な廃棄量を削減し、環境への負担を大きく軽減できます🌱。
分別解体を確実に行うためには、事前の計画と現場監督の的確な判断が不可欠です。
現場では以下のような管理が行われます。
解体前の現地調査(資材の構成・数量確認)
分別計画書の作成
リサイクル業者・運搬業者との連携
搬出記録・マニフェストの作成と保管
これらを一つでも怠ると、法律違反や行政指導の対象になるため、
法令順守と安全管理が同時に求められます。
建設リサイクル法は、単なる規制ではなく、建設業界全体の意識を変える法でもあります。
今では、多くの企業が「ゼロエミッション現場」を目指し、
廃棄物を出さない・再利用するという考え方を取り入れています。
また、分別解体を通じて回収された再生資源は、
道路舗装・基礎材・再生建材など、次の建設現場で再び“命を吹き込まれる”のです。
🔁「壊す」ではなく、「つなぐ」――。
解体工事は、資源循環の出発点となっています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 法律名 | 建設リサイクル法(2002年施行) |
| 対象 | 一定規模以上の建築・改築・改修工事 |
| 義務 | 事前届出・分別解体・再資源化 |
| 効果 | 廃棄量削減・環境保全・資源循環の促進 |
| 意義 | 「解体=再生の始まり」という新しい価値観の定着 |
♻️持続可能な建設業を支えるのは、解体の現場から。
建設リサイクル法は、その第一歩を築いた重要な法律です。
次回もお楽しみに!
安栄株式会社は長野県松本市を拠点に解体工事など総合建設工事を行っております。
お気軽にお問い合わせください。
![]()