-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
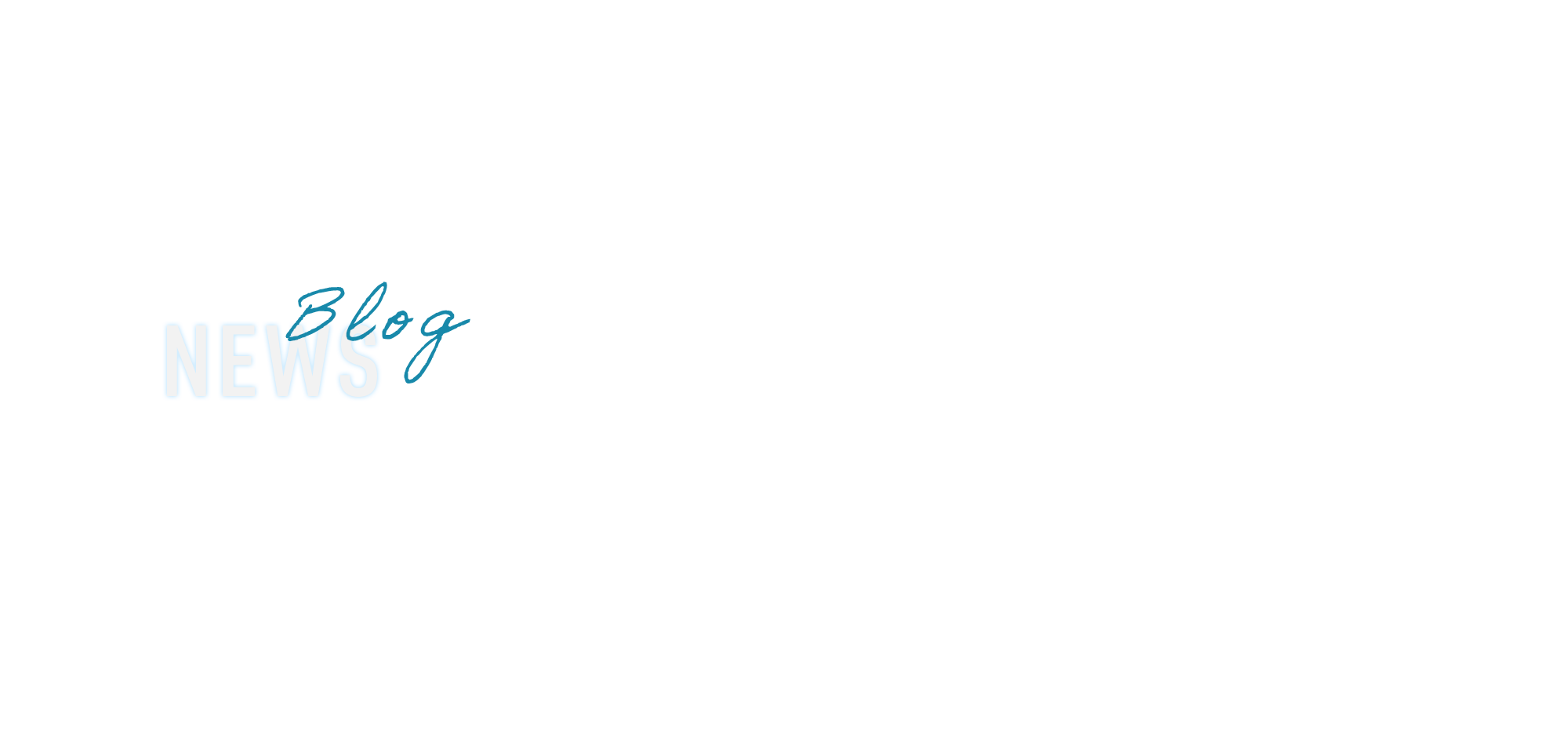
皆さんこんにちは!
安栄株式会社、更新担当の富山です。
~安全・環境・信頼を守るプロの心得~
今回は解体工事の鉄則=絶対に守るべき基本と心構えについて掘り下げます。
解体は、建設業の中でもリスクが高く、専門性が強い仕事です。だからこそ、プロとして守るべき“鉄則”がいくつもあります。
今回は、現場で実際に大切にされている考え方とルールを整理しながらご紹介します。
解体工事では、高所作業・重機作業・倒壊リスクなど、あらゆる危険がつきまといます。
だからこそ、工事前の計画段階が命を守る第一歩です。
事前調査で構造や材質、危険箇所を把握
解体手順の明文化と工程管理
必要な保護具、安全帯、安全ネットの準備
緊急時マニュアルや避難ルートの整備
現場では常にヒヤリ・ハットの共有が行われ、誰もが「想定外」に備える意識を持っています。
現代の解体現場において欠かせないのが、周囲への影響を最小限に抑える工夫です。
騒音・振動を抑えるための機械選定
粉じん飛散を防ぐ散水や防音シートの設置
アスベスト調査の実施と専門業者による除去
廃棄物の分別・リサイクル率の向上
これらを怠ると、近隣トラブル・行政指導・信頼失墜につながります。
だからこそ、“壊す”のではなく、“守る”解体がプロの姿勢なのです。
解体工事は建設工事のスタートライン。遅れはその後のスケジュールに直結します。
近隣への説明や届出のタイミング
重機や人員の稼働計画
突発対応に備えた柔軟なスケジューリング
こうした工程管理の正確さが、円滑な進行と信頼構築を実現します。
解体現場では、重機オペレーター、ガス工、手元作業員など、多様な専門職が連携しています。
そのためには、明確な指示と情報共有、そして相互尊重が不可欠です。
朝礼での全体指示と注意点の共有
危険作業時の声かけ・確認動作の徹底
ベテランと若手の技術伝承とフォローアップ
「連携が安全を生む」――それが解体現場の鉄則です。
解体工事の最後の鉄則は、「目的を見失わない」ということ。
それは単に建物を壊すのではなく、次の時代・新しいまちづくりの第一歩であるという意識です。
「壊す」=「終わり」ではなく、「始まりの仕事」であると自覚しながら、私たちは日々の現場に向き合っています。
解体工事の鉄則は、どれも人命・環境・信頼・未来を守るためのものです。
単なる“力任せの破壊”ではなく、“計画的・安全・丁寧”な作業が、これからの解体工事に求められています。
建物の最期を任される責任ある仕事として、私たちはこれからも、鉄則を守り、信頼される解体業者であり続けたいと考えています。
次回もお楽しみに!
![]()
皆さんこんにちは!
安栄株式会社、更新担当の富山です。
~建物を壊すということの本当の意味~
今回のテーマは、私たちの生活環境と切っても切り離せない「解体工事」の歴史についてです。
建物を「建てる」仕事が注目されがちですが、同じくらい重要なのが「壊す」仕事――それが解体工事です。
私たちの暮らしを支えてきた解体工事が、どのような背景と変遷をたどってきたのか。時代ごとの特徴を交えて、じっくり振り返ってみましょう。
解体工事の概念は、実は古代から存在しています。
日本では、木造建築が主流だったこともあり、**“壊す”というより“分解して再利用する”**という文化が根付いていました。
江戸時代には、建物の部材を組み直す「曳家(ひきや)」や「移築」がよく行われており、職人たちは木材を丁寧に抜いて再利用していました。
現代のように重機で一気に破壊するのではなく、“素材を活かす”という職人気質が重んじられていたのです。
明治時代以降、鉄筋コンクリート(RC)造や鉄骨(S)造の建物が登場し、解体工事の難易度が急上昇します。
特に都市部では高層建築の需要が高まり、「手壊し」だけでは間に合わない時代に。
この頃から人力作業に加えて道具や機械を導入する動きが広まり、くぎ抜きやのこぎり、バールといった工具が解体に使われるようになりました。
また、都市部の再開発や震災の復興工事にともない、一時的に大量の建物を取り壊す必要が生じ、「解体業」が専門化していく契機となります。
第二次世界大戦後、日本は急速な復興とともに建設ラッシュが起こり、「建てては壊す」時代に突入します。
高度経済成長期には、戦前の木造家屋や老朽化した建築物をスピード重視で解体することが求められました。
この時期に普及したのが、油圧ショベル(ユンボ)や鉄球を使った重機解体です。
解体効率が大幅に向上し、重機による“破壊”の時代が幕を開けます。
一方で、粉じんや騒音、アスベストなどの環境・健康への影響が顕在化し、解体工事の「安全」と「周囲への配慮」が新たな課題として浮上します。
2000年代以降、建築リサイクル法や石綿障害予防規則といった法制度の整備が進み、「壊す」から「分けて、守る」へと解体工事の考え方が大きく変わりました。
分別解体による廃棄物の適正処理
粉じん・騒音対策のための養生・散水設備の充実
アスベスト除去の事前調査と報告義務化
現在では、建設業の中でも高度な知識と技能を要する分野となっており、職人たちは「壊す技術」に誇りを持ちながら、安全と環境の両立を目指しています。
解体工事は、単なる“破壊行為”ではありません。
それは、次の建築のための“準備”であり、時代の移り変わりを支えてきた「再出発の第一歩」でもあります。
その歴史をたどると、時代の価値観と技術進化が凝縮された職種であることがよくわかります。
次回は、そんな解体工事の現場で大切にされている「鉄則」について詳しくご紹介します。
次回もお楽しみに!
![]()