-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
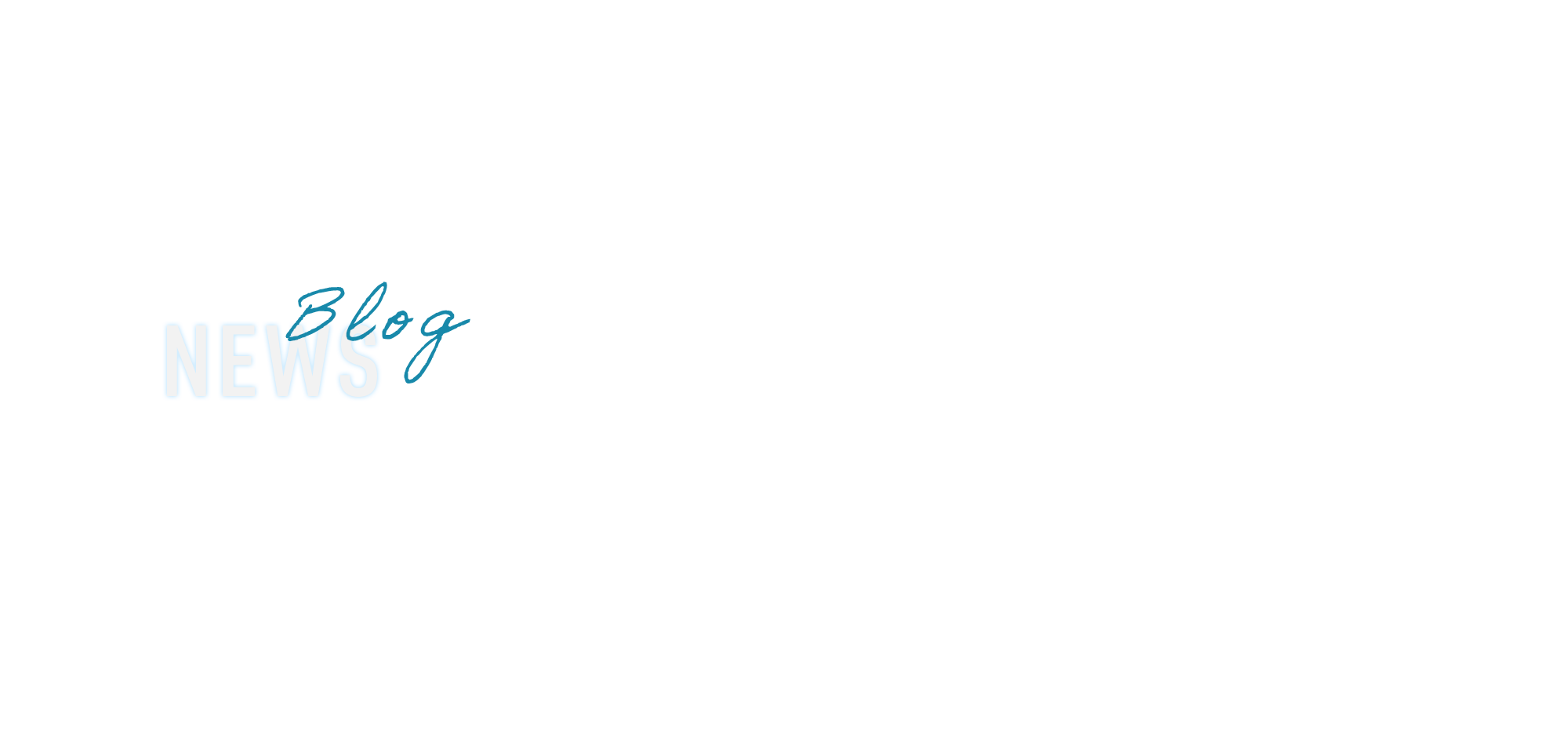
皆さんこんにちは!
長野県松本市を拠点に解体工事など総合建設工事を行っている
安栄株式会社、更新担当の富山です。
前回の記事では、解体工事と環境問題の関係についてお話しました。
今回はさらに一歩踏み込み、「解体工事の未来」について一般的な市場での例を基に考えてみたいと思います。
老朽化インフラが進む一方、技術革新も止まらない今。
この業界は、これからどんな進化をしていくのでしょうか?
現在、日本では1960〜70年代に建てられた建物の大量老朽化が進んでおり、国や自治体は更新・解体の必要性を訴えています。
特に以下の分野では、今後急激な解体需要の増加が見込まれています:
高度経済成長期に建てられた団地・公共施設
老朽化が進んだ橋梁・学校・商業ビル
耐震基準を満たさない建物
この“大解体時代”に備え、解体技術の安全性とスピード、そして環境配慮の高度化がますます求められるようになるでしょう。
近年、建設業界におけるICT・AI・ロボティクスの導入は解体分野にも波及しています。
解体前に建物の状態を3Dデジタルデータで完全に把握し、施工計画を可視化。
これにより「どこから壊すか」「どの順序で安全か」「どこにアスベストがあるか」まで明確に管理可能に。
人が立ち入れない危険区域でも、遠隔で操作できる解体ロボットの開発が進んでいます。
崩落リスクや粉じん暴露などの危険作業を代替する動きが加速中です。
鉄・木・コンクリート・混合廃棄物を、AI画像認識で自動仕分け・搬送するスマート工場も登場。
今後、解体と再資源化の一体運用が加速していくと予測されます。
解体業界も例外ではなく、深刻な人手不足に直面しています。
特に「熟練工の高齢化」と「若年層の離職」が大きな課題です。
ここで期待されているのが、
作業の省力化と自動化
教育のデジタル化(VR解体訓練・シミュレーター)
安全管理のデータ化(IoTセンサー)
これらの導入によって、「危ない・きつい・汚い」という3Kイメージを脱却し、**若手が働きたくなる“スマート解体業”**を実現することが求められます。
これからの解体工事は、「老朽化した建物を壊す」という従来のイメージから、**「新しい街をつくるためのリニューアル工事」**へと大きく意味づけが変わっていくでしょう。
街の“再生”の一歩目を担う仕事として、より多くの人が関心を持ち、支援される立場になるかもしれません。
解体工事の現場には、過去と未来が交錯しています。
古い構造物を手放すことで、次の時代へとつながる“空間”が生まれるのです。
今後ますます求められるのは、
環境への配慮
テクノロジーの導入
若手の育成と多様な働き方
そして何より、「壊す仕事=未来をつくる誇りある仕事」だという再認識。
私たちは、その大切な仕事の担い手として、次のステージへ向かって一歩一歩進んでいきます。
次回もお楽しみに!
長野県松本市を拠点に解体工事など総合建設工事を行っております。
お気軽にお問い合わせください。
![]()
皆さんこんにちは!
長野県松本市を拠点に解体工事など総合建設工事を行っている
安栄株式会社、更新担当の富山です。
今回は、建築物の終わりを担う「解体工事」と、そこに密接に関わる環境問題について掘り下げます。
一見、“壊すだけ”に見える解体工事。
しかし実際には、膨大な廃棄物処理・資源循環・大気や騒音への配慮といった、さまざまな環境的課題が折り重なる、非常に高度で重要な分野です。
建物を解体する際には、多くの物質が発生します。
コンクリート、鉄骨、木材、断熱材、ガラス、石綿、プラスチック、電線、塗装、内装材など…。
中でも注目すべきは以下の3点です:
建設業界は日本国内の廃棄物排出量の中でも非常に大きな割合を占めており、そのうちの約50%が解体工事によって発生しています。
アスベスト(石綿)やPCB(ポリ塩化ビフェニル)など、人体や自然に有害な物質を含む建材が、古い建物には多く残っています。
解体現場の近隣住民にとって、健康被害や生活環境悪化につながる恐れがあるため、周囲への配慮が欠かせません。
こうした問題に対応すべく、現代の解体工事では、次のような環境配慮型の手法が採用されています。
油圧カッター、ブレーカー、ウォールソーなど、従来よりも騒音・振動が少ない重機が登場し、都市部や住宅地での解体がよりスマートに。
現場を防音シートや防塵ネットで囲うことは基本中の基本。
加えて、散水装置やミストガンを使って粉じんの飛散を抑えるなどの先進的なダスト対策も一般的になってきました。
法令に基づき、「木材・金属・コンクリート・廃プラ」などを建物解体中にきっちりと分別し、資源として再利用可能な状態で搬出する工程管理が求められます。
今、私たちの社会は「循環型社会」や「脱炭素社会」への移行を目指しています。
そのなかで、解体工事は単なる“終わりの作業”ではなく、**資源を次へとつなぐ「始まりの作業」**へと意識が変わりつつあります。
再利用可能な資材を丁寧に取り出し、建築資材としてリユースする流れ(=都市鉱山の活用)も始まっています。
壊すことが、次の価値を生む。
それが、これからの解体工事が担う環境への役割です。
次回もお楽しみに!
長野県松本市を拠点に解体工事など総合建設工事を行っております。
お気軽にお問い合わせください。
![]()